現場作業や物流業界での必須資格の一つが「フォークリフト運転技能講習修了証(1トン以上)」です。重い荷物を安全かつ効率的に運搬するためには、確かな知識と技術が求められます。今回は、筆者が実際にこの講習に参加している最中の体験をもとに、フォークリフト免許取得までの流れや講習の実態、感想を詳しく紹介します。
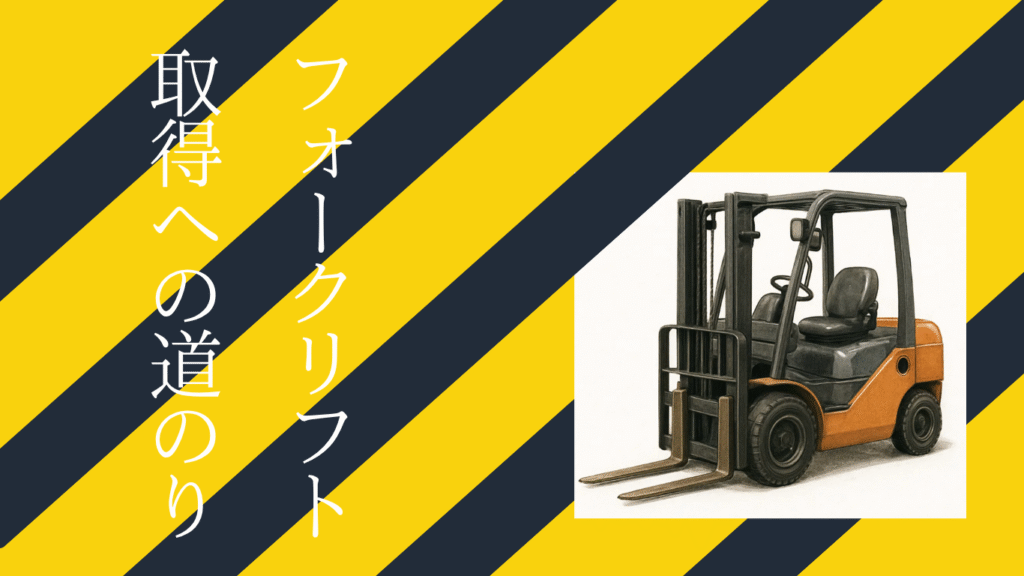
■ 受講申込みと会場選び
まず最初のステップは、受講場所を決めることです。筆者は「キャタピラー九州株式会社」が実施する講習を選びましたが、自動車学校の中にもフォークリフト技能講習を実施しているところがあります。申込みは各講習機関の公式ホームページまたは窓口で行えます。
人気のある講習会場ではすぐに定員が埋まってしまうことも多いため、早めの申込みがポイントです。特に週末(土日)開催のコースは、社会人からの人気が高く、競争率も上がります。
■ 普通免許があれば31時間・4日で取得可能!
講習を受けるにはいくつかの条件がありますが、基本的には普通自動車運転免許を所持していればOK。この場合、法定講習時間は31時間で済み、最短4日間のコースで修了できます。逆に、免許を持っていない場合は講習時間が2倍以上(約4日×2)になるので、取得ハードルがぐっと高くなります。
筆者が選んだのは、土日を利用した週末4日コース。社会人として働きながらでも、休日に集中して受講できるスケジュールです。
■ 少人数制でじっくり学べる体制
講習は10人1組で構成され、担当講師が1名つきます。使用するフォークリフトは1台のみ。つまり、実技講習中は1人ずつ順番に練習する形式となるため、待ち時間がかなり長くなります。練習場所は事務所裏のちょっとしたスペースで行われました。実際に走らせる現場の両端にはショベルの先に取り付けるジョイントや様々なものが置かれていたのでもう少し整理された場所で練習したいですね。
この形式にはメリットとデメリットがあります。講師の目が行き届きやすい点や、他人の操作を見て学べるという利点もある一方、「自分の番が来るまでずっと待機」という退屈さや緊張感もあります。1人あたりの実技時間は多く見積もっても1日約3時間程度で、その他の時間は基本的に見学と待機時間です。
■ 講習初日:学科と試験
講習初日は、朝8時30分までに集合し、学科中心の講義がスタートします。座学では、フォークリフトの構造、安全運転の基本、荷役における注意点、法規などを学びます。黒板やスライドを使った講義に加え、事故例の映像なども交えて、現場での危険性について理解を深めていきます。
その日の最後には、学科試験があります。講義の内容をしっかりと聞いていれば解ける内容で、問題数も多くありません。講師の方がテキストを元に出題場所を教えてくれますのでそこまで心配する必要はないでしょう。とはいえ、数問でもミスが重なると不合格になることもあるため、油断は禁物です。
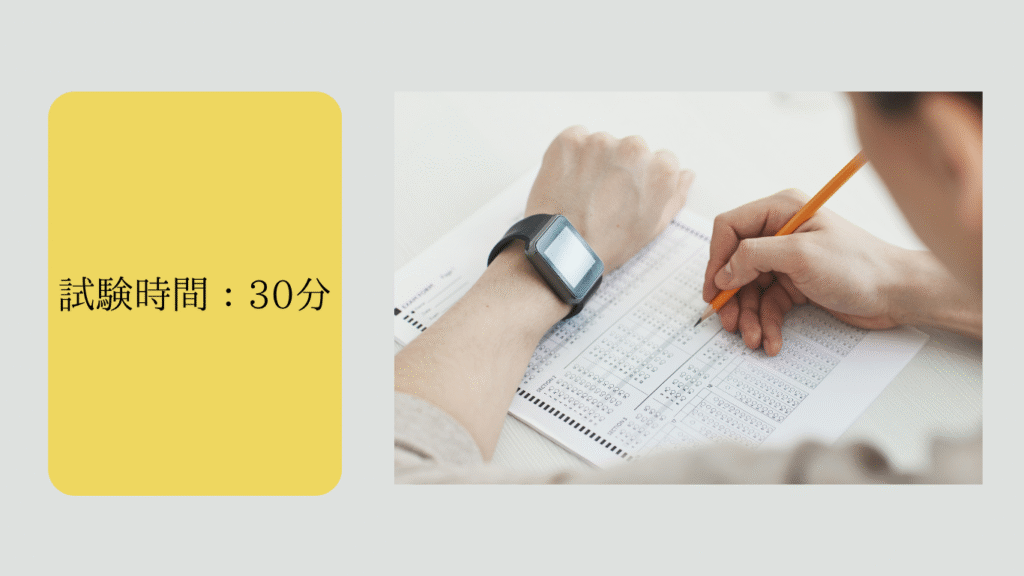
■ 2日目以降:実技練習スタート!
2日目からはいよいよ実技講習が始まります。朝7時50分集合、8時から開始と、非常に朝が早い点も要注意です。
最初はフォークリフトの乗降方法や操作レバーの説明、安全確認の手順といった基礎を学びます。これは自動車学校での運転実習と似たような内容で、発進前の安全確認、ミラーの調整、周囲確認などが重要視されます。
実際の運転では、前進・後進の直進運転に加え、S字カーブの走行練習も行います。パイロン(コーン)を設置したコース内を、荷物を持って走行したり、方向転換したりする中で、正確さと安全確認の徹底が求められます。
■ 待ち時間の長さと集中力の維持が課題
実技は1人ずつ順番に行うため、他の9人は見学や待機時間になります。1日の講習時間は8時から17時40分までと長丁場ですが、実際にフォークリフトに乗って操作できる時間は非常に限られています。
この点は、受講者にとっては「体力よりも集中力と忍耐力が必要な講習」と言えるかもしれません。座っている時間が多いため、一見楽そうに見えますが、長時間じっと待ち続けるのは意外と大変です。
また、他の受講者の運転を見ることで自分の理解を深めることもできるため、待機時間も無駄にはなりません。ただし、寒暖差の激しい季節や、屋外講習の場合は体調管理に注意が必要です。
■ 実技試験とまとめ
最終日には、実技試験が行われます。現在二日目講習終わり次週また再開です。練習した内容をもとに、コースを作る予定でフォークリフトの安全操作、S字走行、荷物の持ち上げ・移動などを行います。
講習期間はたったの4日間ですが、内容は非常に濃く、1日中しっかりと詰め込まれるスケジュールです。そのため、精神的にも肉体的にも少なからず負担を感じる講習ではありますが、「たった4日で一生使える技能が手に入る」と思えば、十分に価値のある資格だと実感できます。
■ 現在も講習継続中!
筆者は現在もこの講習に参加している最中ですが、これまでの体験を通して、「いかに安全が大切か」「効率よりも確実な操作が求められるか」を日々学んでいます。
これから受講を検討している方には、早めの申し込みと、講習期間中の生活リズム調整、そして講義・実技ともに真剣に取り組む意識が大切だとお伝えしたいです。


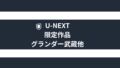

コメント